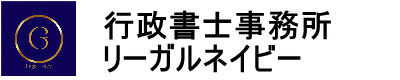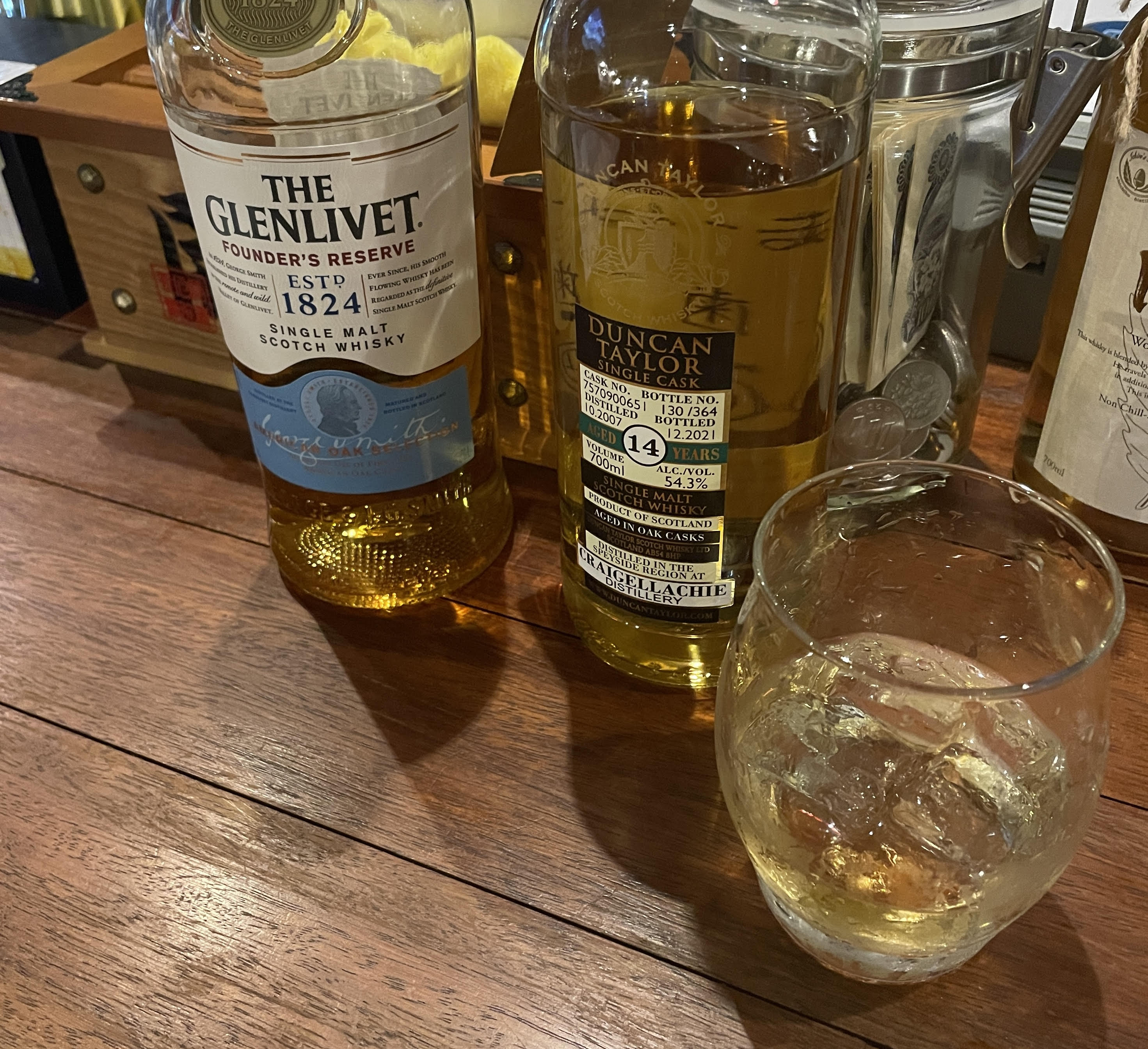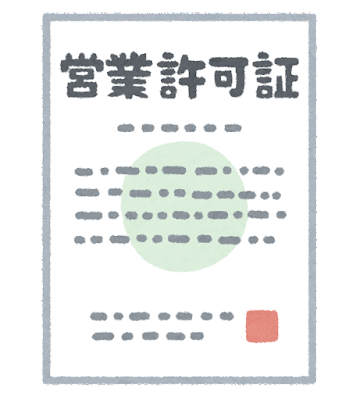建設業許可申請

建設業許可の概要
建設業許可が必要な工事とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な工事※を請負う場合を除いて建設業許可を受けなければいけません。
※軽微な工事とは
①建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は、延面積が150㎡未満の木造住宅工事
②上記①以外の工事の場合:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
許可の有効期間について
許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年目が経過する日の前日で満了します。この場合に、許可期間の満了日が日曜祝日であってもその日で満了してしまいます。
例:許可日が2023年4月1日であれば、満了日は2028年3月31日ということになります。
なので引き続き建設業を営もうとする場合は、許可満了日の30日前までに許可更新の手続きをしなければいけません。
許可の区分
国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い
建設業許可には国土交通大臣の許可または、都道府県知事の許可の2つの区分があります。
建設事業者が取得する許可が大臣許可なのか知事許可になるのかについては、営業所※の設置状況によって判断されます。
2以上の都道府県にまたがって営業所を設けて営業しようとする場合は大臣許可が必要になります。
1の都道府県の区域のみに営業所を設けて営業する場合は、知事許可となります。
※営業所とは、本店または、支店もしくは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
特定建設業許可は、発注者から直接請負った元請事業者が、その1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする建設事業者が取得する許可です。
一般建設業許可は、上記以外の事業者が取得する許可です。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するにあたり、5つの要件をクリアしなければいけません。
注)この要件に関しては、情報元によっては6つと明記されている場合もあります。これに関しては、著者等のさじ加減であるので要件の内容自体が大きく異なるわけではありません。ですので要件の数にこだわる必要はありません。
要件1 経営業務管理責任者がいること
建設業の経営管理を適正に行う能力を有する者のことをいいます。
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
取得したい許可の建設工事について専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所でその工事に専属的に従事する者をいいます。
要件3 適切な社会保険に加入していること
法人の場合は、原則加入しておく必要があります。個人事業主の場合で常時5人以上の従業員を雇用している場合は、原則加入する必要があります。
要件4 財産的基礎があること
①自己資本額が500万円以上あること
②500万円以上の資金を金融機関から借りられる能力があること
➂許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
以上3つのいずれかに該当していることが求められます。
注)➂については、既に建設業許可を受けている事業者が対象です(許可更新の要件)。
要件5 誠実性があること
許可申請者について不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。法人の場合は、役員や支配人、営業所長等に、個人の場合は申請者本人、支配人、営業所長等にこの誠実性が求められます。
この要件は簡単に理解していただければ大丈夫です。
+@欠格要件に該当しないこと
建設業許可を取得しようとする者が一定の欠格要件に該当していないことが求められています。法人の場合は、役員や議決権を5%以上有する株主も含まれます。個人の場合は、申請者本人や支配人等が含まれます。
欠格要件の一例:禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
注)先に要件の数が情報元によって異なると説明しました。要は、この欠格要件を要件数に数えるか否かの違いです。本記事では要件数を5つとして、欠格要件を+@の位置づけで案内していますのでご理解ください。
許可取得までの流れ
許可取得までの流れ
①電話予約
弊所でお役所の担当者との面談日時を調整します。
②面談日時指定
ご依頼者様と日程調整のうえ、面談日時を調整します。
③面談日の1週間前までに申請書類を提出
弊所で申請書類を揃え、提出します。必要に応じてご依頼者様にも書類準備へのご協力をお願いすることがあります。
➃書類審査
お役所での書類審査
⑤面談及び受付
書類の内容に不備等がなければ受理されます。
⑥欠格調査及び電算処理(約2~3週間かかります)
県警での照会等により調査が行われます。また、場合によっては書類の補正が必要になります。弊所の行政書士で対応いたします(内容によってはご依頼者様にも連絡させていただく場合があります)。
⑦許可通知書発送(約1ヶ月後)
許可通知書を申請書控えとともにご依頼者様へ簡易書留郵便にて送付されます。
最後に
一定規模以上の工事を請負う場合は、都道府県知事、又は国土交通大臣の許可が必要です。
この許認可には、いくつかの要件があり、それをクリアしている必要があります。また、要件を証明する書類をそろえる必要もあります。
許認可取得後にも一定期間ごと、変更があればその都度届出や申請が必要になる場合があります。
このように許認可をとるためにはたくさんの時間と労力を要します。
申請に必要な期間にもご注意ください。
当事務所は、建設業許可の要件や、許可条件を満たしているかの調査をし、必要書類の作成及び代理申請を行います。
お悩みの際は、当事務所へお気軽にご相談ください。